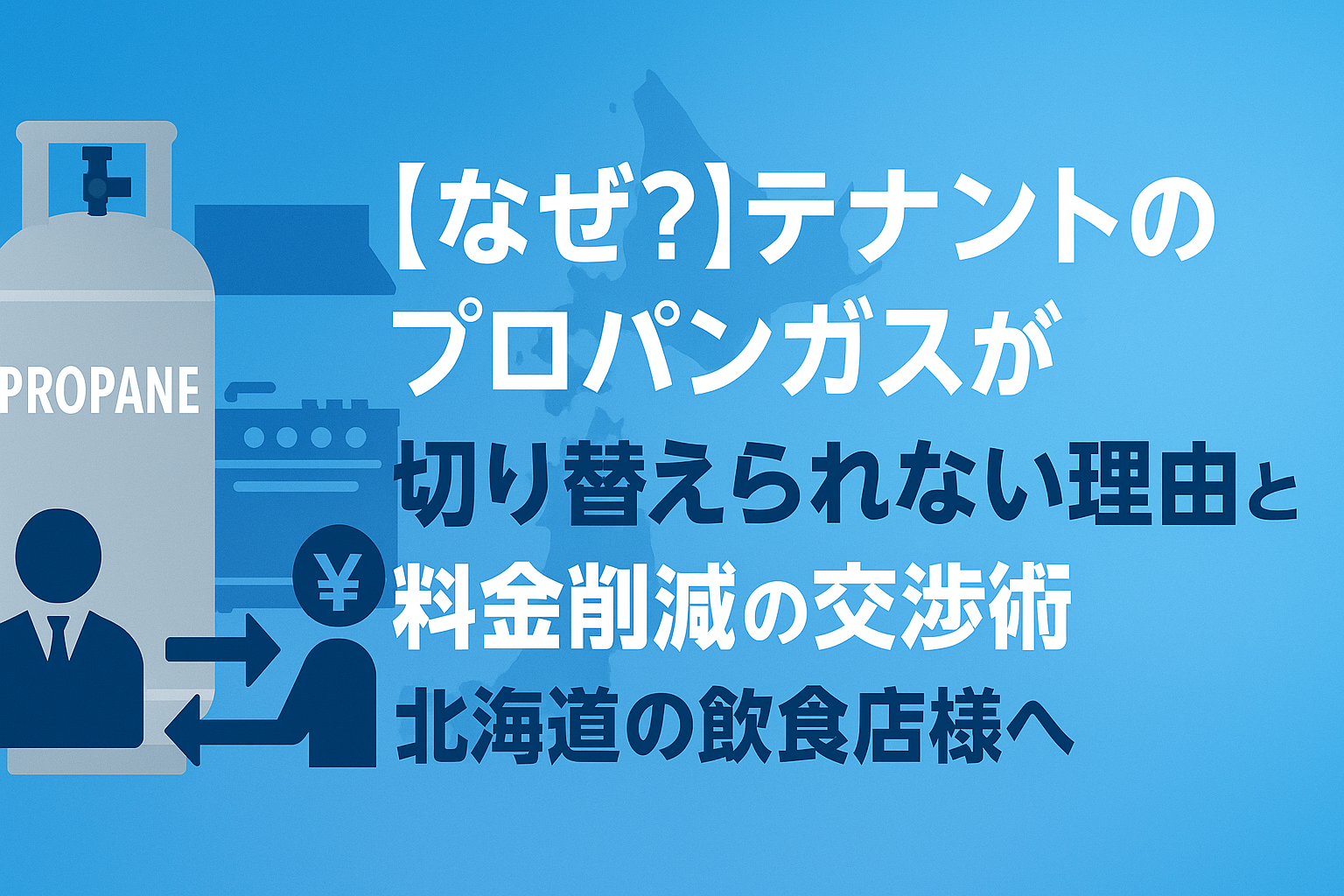北海道で飲食店を経営されているオーナーの皆様。厳しい寒さの中で、毎月の光熱費、特にプロパンガス(LPガス)の料金の高さに頭を悩ませてはいませんか?
「近隣の店はもっとガス代が安いらしい」「ガス会社を切り替えれば料金が下がると聞いた」…そんな情報を耳にするたびに、「なぜ、自分の店ではガス会社を自由に選べないのだろう?」と疑問に感じたことはないでしょうか。
実は、テナントで入居している店舗がプロパンガス会社を簡単に切り替えられないのには、明確な理由が存在します。それは、多くの飲食店オーナー様が知らない、大家さん(建物オーナー)とガス会社との間に結ばれた、ある“特別な契約”が関係しているのです。
このコラムでは、長年多くの経営者を悩ませてきた「プロパンガス切り替えの壁」の正体を、専門的な知識がない方にも分かりやすく、そして詳しく解説していきます。この記事を読み終える頃には、なぜガス会社が変えられないのか、その根本的な仕組みをご理解いただけるはずです。
ガス料金という経営の根幹に関わるコスト削減の第一歩として、ぜひ最後までお付き合いください。
第1章:プロパンガスの「料金」と「自由化」の基本を知る
まず、なぜプロパンガスの料金がこれほどまでに話題に上るのか、その基本的な背景からご説明します。すでにご存知のオーナー様も、知識の再確認としてご一読ください。
1-1. プロパンガスは「自由料金」。だからこそ価格差が生まれる
日本の家庭や店舗で使われるガスには、大きく分けて「都市ガス」と「プロパンガス(LPガス)」の2種類があります。この二つの最大の違いは、料金の決定方法にあります。
- 都市ガス: 地中のガス管を通じて供給されるガスです。かつては政府の認可が必要な「規制料金」でしたが、2017年に全面自由化されました。しかし、インフラ整備に莫大な費用がかかるため、参入企業が限られ、地域独占的な性質が残っています。料金は比較的安定していますが、供給エリアが都市部に限定されます。
- プロパンガス(LPガス): ガスボンベを各施設に設置して供給するガスです。都市ガスが通っていない地域で広く利用されています。そして、ここが最も重要なポイントですが、プロパンガスは1997年から既に料金が自由化されており、販売店が自由に価格を設定できる「自由料金制」です。
自由料金制ということは、ガソリンや食料品と同じように、どの会社から買うか、いくらで買うかを消費者が自由に選べる、ということです。そして、販売店ごとに仕入れ値、配送コスト、人件費、そして利益が異なるため、同じ地域であってもA社とB社ではガス料金に大きな差が生まれるのです。
特に、ガスを大量に使用する飲食店にとって、この価格差は経営に直接的な影響を与えます。従量単価(ガス1m³あたりの単価)が100円違えば、月間200m³使用する店舗では、単純計算で毎月20,000円、年間では240,000円もの差額が発生するのです。
だからこそ、多くの飲食店オーナー様が「より安いガス会社に切り替えたい」と考えるのは、至極当然の経営判断と言えるでしょう。
1-2. 「自由に選べるはず」なのに、なぜ変えられないのか?
「自由料金制で、消費者が自由に選べるのなら、今すぐ安い会社に電話して切り替えればいいじゃないか」
そう思われるのも無理はありません。しかし、戸建て住宅なら簡単なこの「切り替え」が、アパートやマンション、そしてテナントビルといった集合住宅・施設になると、途端に難しくなります。
その最大の障壁となっているのが、次章で詳しく解説する「無償貸与契約」という、業界特有の契約形態なのです。
第2章:切り替えを阻む壁の正体 – 「無償貸与契約」のカラクリ
テナント入居者がプロパンガス会社を切り替えられない根本的な原因は、ほぼ100%、この「無償貸与契約(むしょうたいよけいやく)」にあります。一体どのような契約なのか、その仕組みを紐解いていきましょう。
2-1. 無償貸与契約とは何か?
無償貸与契約とは、一言で言うと「ガス会社が、ガス設備の設置費用を肩代わりする代わりに、その建物でのガス供給を長期間独占する契約」のことです。
通常、アパートやテナントビルを新築・改築する際、ガスを供給するためには様々な設備が必要になります。
- 供給設備: ガスボンベ庫、ガスメーター、ガス管など
- 消費設備: 給湯器、ガスコンロ、ガスオーブンなど(※厨房機器は店舗側負担が多いですが、給湯器などは契約に含まれることがあります)
これらの設備をすべて大家さん(建物オーナー)が自己資金で用意しようとすると、規模にもよりますが、数百万円から、時には一千万円を超える初期投資が必要となります。
そこで、ガス会社が大家さんにこう提案するのです。
「大家さんの初期投資は不要です。これらのガス設備は、すべて当社が無償で設置・所有します。その代わり、今後10年~15年間は、当社のガスをこの建物の入居者全員に使ってもらう、という契約を結んでください」
これが「無償貸与契約」の基本的なスキームです。大家さんにとっては、建築時の初期費用を大幅に削減できるという非常に大きなメリットがあります。一方、ガス会社にとっては、莫大な設備投資をしても、その後10年以上にわたって安定的にガス料金を徴収できるため、投資分を回収し、さらに利益を上げることができるのです。
ポイントは、「ガス設備は大家さんの所有物ではなく、ガス会社の所有物である」という点です。 テナントとして入居しているオーナー様は、大家さんの所有物だと思っているかもしれませんが、壁の中を通るガス管や、外に設置されているガスメーターは、既存のガス会社の資産なのです。
2-2. なぜ「無償貸与」が切り替えの障壁になるのか?
この契約のどこに問題があるのでしょうか。それは、契約の「縛り」にあります。
無償貸与契約には、通常10年~15年といった長期の契約期間が設定されています。そして、もし大家さんが契約期間の途中で解約し、他のガス会社に切り替えようとした場合、高額な違約金が発生するのです。
この違約金は、一般的に「設備残存価格(ざんそんかかく)」と呼ばれます。
ガス会社は、無償で設置した設備の費用を、毎月のガス料金に少しずつ上乗せして回収しています。例えば、200万円の設備投資を10年(120ヶ月)で回収する計画だとします。もし5年(60ヶ月)で解約された場合、ガス会社はまだ半分の100万円しか回収できていません。
そのため、解約時にはこの未回収分である100万円を、「設備残存価格」として大家さんに一括で請求するのです。
大家さんの立場になってみてください。テナントから「ガス代が高いから会社を変えてほしい」と言われても、そのためには100万円、200万円といった大金をガス会社に支払わなければなりません。これでは、よほどの理由がない限り、ガス会社の変更に同意するのは難しいでしょう。
これが、テナント入居者である飲食店オーナー様が、いくら「ガス会社を切り替えたい」と願っても、大家さんや管理会社から「うちは特定のガス会社と契約しているので変更できません」と断られてしまう、最大の理由なのです。
つまり、飲食店オーナー様は、自分が入居するずっと前に大家さんとガス会社の間で結ばれた契約によって、ガス会社を選ぶ自由を実質的に奪われている状態にある、と言えます。
2-3. この契約は違法ではないのか?
「そんな一方的な契約が許されるのか?」と憤りを感じる方もいらっしゃるかもしれません。
結論から言うと、この無償貸与契約自体は、現在の法律では違法ではありません。大家さんの初期費用負担を軽減し、LPガスの普及に貢献してきたという側面も、業界側は主張しています。
しかし、その運用方法には問題点が指摘されています。
- 料金設定の不透明性: ガス会社は、設備投資の回収分をガス料金に上乗せしますが、その内訳が消費者に明示されることはほとんどありません。相場よりかなり高い料金が設定されていても、消費者は気づきにくいのが現状です。
- 長期の契約縛り: 10年~15年という期間は、消費者の選択の自由を過度に制限しているという批判があります。
- 情報の非対称性: 多くの大家さんや入居者は、このような契約の存在や仕組みを十分に理解しないまま契約・入居しているケースが少なくありません。
これらの問題から、消費者保護の観点で見直しを求める声も上がっており、経済産業省も過度な契約については是正を促す動きを見せていますが、根本的な解決には至っていないのが実情です。
第3章:北海道の飲食店オーナーが直面する厳しい現実
この「無償貸与契約」の仕組みは、全国共通の問題ですが、特に北海道で飲食店を経営するオーナー様にとっては、より深刻な影響を及ぼすことがあります。
3-1. 大量のガス消費と高い料金単価のダブルパンチ
飲食店、特にラーメン店、中華料理店、レストランなど、強い火力を長時間必要とする業態では、ガスの使用量が家庭の比ではありません。月々のガス使用量が300m³、500m³を超えることも珍しくありません。
ここに、無償貸与契約によって高止まりしたガス料金単価が掛け合わされます。
例えば、北海道のプロパンガスの適正価格の従量単価が350円~450円/m³程度だとします(※価格は常に変動します)。しかし、無償貸与契約で縛られている物件では、600円、700円といった高い単価が設定されているケースも散見されます。
【月間500m³使用した場合の料金シミュレーション】
- 適正単価(400円/m³)の場合:
- 従量料金:500m³ × 400円 = 200,000円
- 基本料金(仮に2,000円とする):2,000円
- 合計:202,000円
- 割高な単価(650円/m³)の場合:
- 従量料金:500m³ × 650円 = 325,000円
- 基本料金(仮に2,000円とする):2,000円
- 合計:327,000円
この差額は、月々125,000円、年間で実に1,500,000円にもなります。これは、もはや無視できない経営コストです。人件費や食材費の削減には限界がありますが、ガス料金は、もし切り替えが実現すれば、経営努力なしに大幅なコスト削減が可能な“固定費”なのです。
3-2. 厳しい冬が追い打ちをかける「暖房・給湯」コスト
北海道の経営環境をさらに厳しくするのが、長く厳しい冬の存在です。
店舗の暖房や、大量の洗い物で使うお湯を沸かすための給湯にも、プロパンガスは使われます。冬場は当然、これらの使用量が跳ね上がり、ガス料金全体を押し上げます。
夏のガス代の1.5倍、2倍になることも珍しくありません。割高なガス料金単価のまま冬を迎えることは、経営者にとって大きなプレッシャーとなります。
3-3. 気づかぬうちに経営を圧迫している
多くのオーナー様は、日々の忙しさに追われ、ガス料金の検針票をじっくりと確認する余裕がないかもしれません。「ガス代はこんなものだろう」と、知らず知らずのうちに適正価格の何倍もの料金を支払い続けている可能性があるのです。
その支払っている差額分が、本来であれば、新しい厨房機器の導入、従業員の給与アップ、あるいはオーナー様自身の利益になったかもしれないお金だと考えると、この問題を放置しておくことは、非常にもったいないと言えるでしょう。
第4章:不可能ではない!ガス会社切り替えへの具体的なロードマップ
「仕組みは分かった。でも、結局は大家さん次第で、自分には何もできないのか…」
そう諦めてしまうのは、まだ早いです。確かに簡単ではありませんが、テナント入居者から行動を起こし、ガス会社の切り替えに成功した事例も存在します。ここでは、そのための具体的なステップと、交渉のポイントを解説します。
ステップ1:現状把握 – 自分の店のガス料金は本当に高いのか?
交渉を始める前に、まずは客観的な事実を固めることが重要です。
- 検針票の確認:
- 過去数ヶ月分のガス検針票を用意してください。
- 見るべきは「基本料金」と「従量単価」です。検針票に単価が明記されていない場合は、「(請求額 – 基本料金)÷ ガス使用量」で算出できます。
- 夏と冬の料金を比較し、季節による変動も把握しておきましょう。
- 地域の相場を調べる:
- インターネットで「北海道 プロパンガス 平均価格」「(あなたの市町村名) LPガス 料金」などと検索し、地域の料金相場を調べます。複数の料金比較サイトを参考にすると、より客観的な価格が見えてきます。
- この時、家庭用料金と業務用(店舗用)料金は異なる場合があるので注意が必要です。
- 他のガス会社から見積もりを取る:
- これが最も効果的です。地域の他のガス会社に数社連絡を取り、「現在の使用量と料金を伝えた上で、もし切り替えた場合の料金見積もり」を依頼します。
- 「今のビルは契約で変えられないかもしれないのですが…」と正直に伝えつつ、あくまで参考としての見積もりをもらいましょう。快く応じてくれる会社は、切り替えに協力的である可能性が高いです。
これらの情報収集によって、「自分の店が、相場や他社見積もりに比べて、月に〇万円、年間で〇〇万円も高く支払っている」という具体的な数字を把握することが、交渉の第一歩となります。
ステップ2:情報収集 – 大家さんとの契約内容を探る
次に、切り替えの最大の障壁である「無償貸与契約」の具体的な内容を確認する必要があります。これは大家さんや管理会社に直接ヒアリングするしかありません。
- 聞き方のポイント:
- 感情的にならず、あくまで「経営コスト削減の一環として検討しており、ご相談したい」という低姿勢で切り出します。
- 「ガス代が非常に高く経営を圧迫している。調べたところ、ガス会社の切り替えで大幅に安くなる可能性があると分かった。つきましては、現在のガス会社との契約状況を教えていただけないでしょうか」と、丁寧にお願いしましょう。
- 確認すべき項目は以下の通りです。
- 無償貸与契約の有無
- 契約期間(いつからいつまでか)
- 契約満了まであと何年か
- 途中解約した場合の違約金(設備残存価格)がいくらになるか
大家さん自身も契約内容を正確に把握していない場合があります。その場合は、大家さんからガス会社に問い合わせてもらうよう、お願いする必要があります。
ステップ3:交渉準備 – 「大家さんのメリット」を提示する
情報が揃ったら、いよいよ大家さんへの本格的な交渉準備です。重要なのは、「テナントの都合」だけを押し付けるのではなく、「大家さんにとってもメリットがある提案」をすることです。
大家さんが切り替えを渋る理由は、主に以下の3つです。
- 違約金の支払いが発生する
- 手続きが面倒くさい
- 今のガス会社との付き合いが長い(義理)
これらの懸念を払拭できる提案を用意します。
- 提案1:違約金の負担を解決する
- 新しいガス会社の中には、既存のガス会社への違約金(設備残存価格)を肩代わりしてくれる会社があります。ステップ1で見積もりを取った会社に、「残存価格が〇〇円あるのですが、これを負担して切り替えることは可能ですか?」と相談してみましょう。
- もし新しいガス会社が違約金を負担してくれるなら、大家さんの金銭的負担はゼロになります。これは交渉における最強のカードです。
- 提案2:大家さんの手間を最小限にする
- 「ガス会社とのやり取りや手続きは、すべてこちら(テナント側)と新しいガス会社で進めますので、大家さんにはご承認いただくだけで結構です」と伝え、大家さんの手間を極力減らすことをアピールします。
- 提案3:他のテナントと協力する
- 同じビルに他の飲食店や事務所などが入っている場合、共同で交渉するのは非常に有効です。複数のテナントが同様に高いガス料金に悩んでいることを示せば、大家さんも問題を軽視できなくなります。「ビル全体の光熱費が下がることは、今後のテナント募集においても有利になりますよ」と、ビル全体の資産価値向上に繋がる視点を提示するのも良いでしょう。
- 提案4:長期的な視点を提示する
- 「このまま高いガス料金が続けば、うちの店の経営が立ち行かなくなり、最悪の場合、退去せざるを得ません。そうなれば、大家さんにとっても空室リスクが発生します。ガス料金を適正化することは、私たちがこの場所で長く商売を続けるためにも不可欠です」と伝え、テナントの安定経営が大家さんの安定収入に繋がることを理解してもらいます。
ステップ4:いざ交渉へ – 感情的にならず、論理的に
準備が整ったら、大家さんや管理会社との交渉に臨みます。
- 資料を用意する: 現在のガス料金の検針票、地域の相場価格データ、新しいガス会社からの見積書など、客観的なデータを揃えて提示します。
- 協力的な姿勢を貫く: あくまで「相談」というスタンスを崩さず、高圧的な態度は避けます。大家さんとの良好な関係を維持することが、最終的な目標達成への近道です。
- 一度で諦めない: 交渉は一度で終わらないかもしれません。大家さんにも考える時間が必要です。粘り強く、しかし誠実に対話を続けていくことが重要です。
第5章:交渉が難しい場合に、今すぐできること
大家さんとの交渉がどうしても進まない、あるいは違約金が高額すぎて切り替えが現実的ではない、というケースも残念ながら存在します。しかし、それでも諦める必要はありません。ガス代を削減するために、今すぐ取り組める対策もあります。
5-1. 現在のガス会社への「値下げ交渉」
他社への切り替えが難しい場合でも、現在のガス会社に直接、料金の値下げを交渉する価値はあります。
- 交渉のコツ:
- 他社から取った安い見積書を提示し、「このくらいの価格にならなければ、契約満了後には切り替えを検討せざるを得ない」と伝えます。
- ガス会社としても、優良な顧客である飲食店を手放したくはありません。特に長年利用している顧客であれば、ある程度の値下げに応じてくれる可能性は十分にあります。
- 一度の値下げで満足せず、定期的に料金の見直しを要請することも重要です。
これは根本的な解決ではありませんが、応急処置として月々のコストを数千円~数万円下げる効果が期待できます。
5-2. 徹底した「省エネ」の実践
ガスの単価を下げられないなら、使用量そのものを減らすしかありません。日々の厨房業務の中に、無駄が隠れていないか見直してみましょう。
- 厨房での省エネ
- 適正な火力調整: 必要以上の強火はガスの無駄遣いです。鍋底から炎がはみ出さない程度の火力を心がける。
- 調理手順の効率化: まとめられる下ごしらえは一度に行い、コンロの点火時間を短縮する。
- 蓋や落し蓋の活用: 煮込み料理などでは蓋をすることで熱効率が上がり、調理時間とガス使用量を削減できます。
- 高効率な厨房機器への更新: 最新のガスコンロやフライヤーは、古い機種に比べて熱効率が格段に向上しています。初期投資はかかりますが、長期的に見ればガス代の削減で元が取れる可能性があります。
- 給湯での省エネ
- 給湯温度の適切な設定: 食器洗浄機で使うお湯など、必要以上に高い温度に設定していないか見直します。温度を1~2度下げるだけでも、ガス使用量は変わってきます。
- 節水型シャワーヘッドの利用: 食器の予洗いで使うシャワーなどを節水型に変えることで、使用するお湯の量を減らし、結果的にガス代の節約に繋がります。
これらの地道な努力も、積み重ねることで着実なコスト削減効果を生み出します。
まとめ:諦めずに、まず一歩を踏み出すことが経営改善の鍵
テナントで入居している飲食店がプロパンガス会社を簡単に切り替えられない理由。それは、大家さんと既存のガス会社との間で結ばれた「無償貸与契約」という、いわば“見えない鎖”が原因です。
この契約は、大家さんにとっては初期投資を抑えられるメリットがある一方で、そのツケをテナント入居者が「相場より高いガス料金」という形で支払わされている、という構造的な問題を抱えています。
しかし、この問題は決してアンタッチャブルなものではありません。
- 仕組みを正しく理解する
- 自店の料金と地域の相場を客観的に把握する
- 違約金を負担してくれる新しいガス会社を見つける
- 大家さんのメリットも提示しながら、論理的かつ誠実に交渉する
これらのステップを踏むことで、不可能だと思われたガス会社の切り替えを実現できる可能性は十分にあります。
北海道の厳しい経済環境の中、日々奮闘されている飲食店オーナー様にとって、毎月数万円、年間で数十万円にもなるガス料金の削減は、経営に大きなインパクトを与えるはずです。その浮いたコストは、新たなメニュー開発、サービスの向上、そして何よりもオーナー様ご自身の生活を豊かにするために使うことができます。
「うちの店は無理だ」と諦める前に、まずは検針票を手に取り、地域のガス料金を調べてみることから始めてみませんか。その小さな一歩が、あなたの店の未来を大きく変えるきっかけになるかもしれません。
このコラムが、北海道で頑張るすべての飲食店オーナー様の一助となることを、心から願っております。