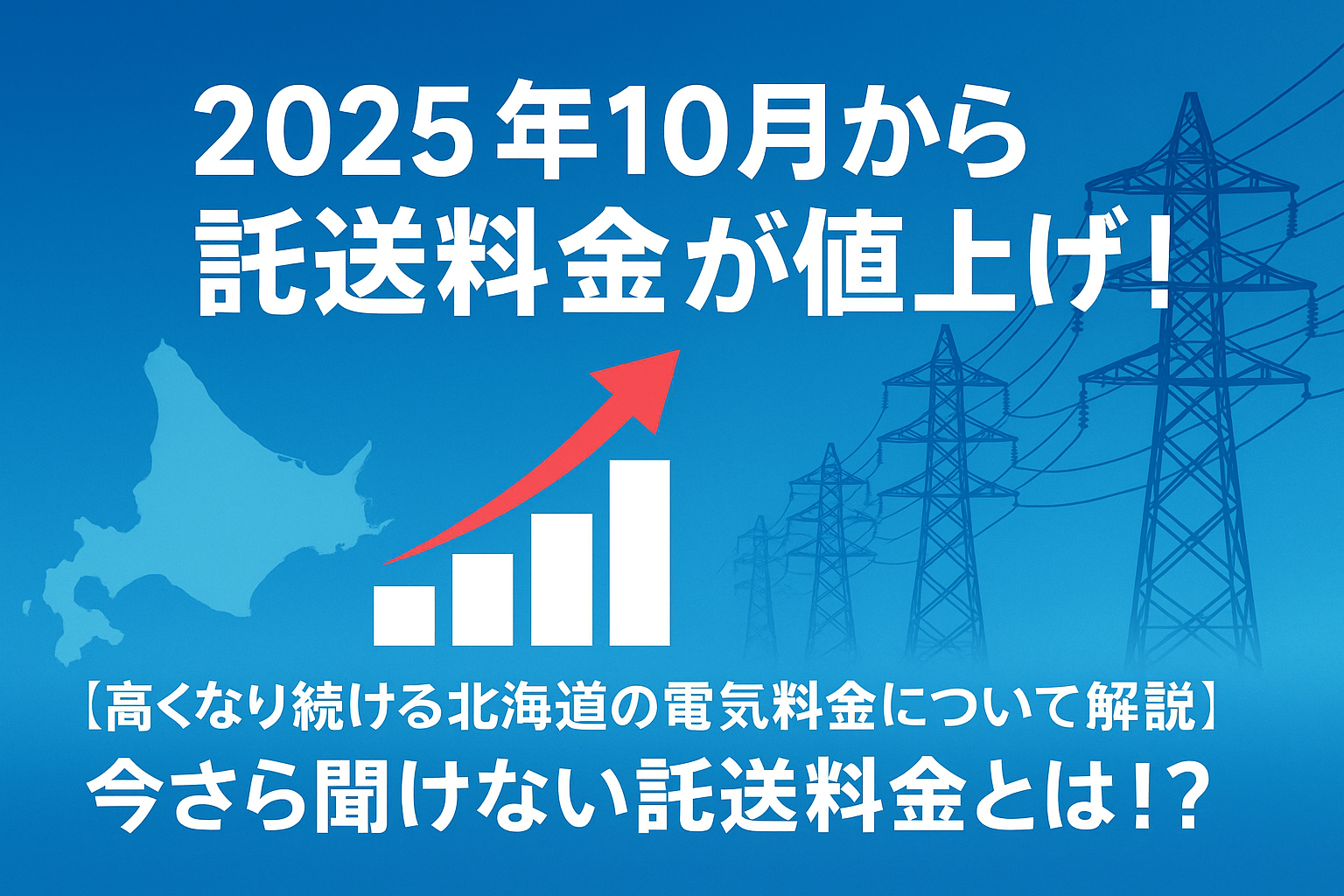北海道では近年、電気料金の値上げが大きな課題となっています。特に2025年10月から実施される託送料金(送電線など電力網の使用料金)の値上げは、多くの企業にとって無視できない負担増となる見込みです。例えば札幌市内のある食品加工工場では、月間約50,000kWhの電力を使用しており、今回の託送料金改定によって月々の電気代が数万円規模で増加する試算となっています。電気代に占める託送料金の割合は約3割にも達するため、その値上げは企業の光熱費に直接響き、経営を圧迫しかねません。
本コラムでは、北海道における電気値上げの仕組み、とりわけ託送料金の値上げについて一次情報に基づき解説します。
託送料金とは何か、その料金算定に適用されるレベニューキャップ制度とはどのような制度か、そしてなぜ今回託送料金が上がるのか。基本的な知識を整理し、2025年10月からの具体的な値上げ幅についても明示します。また、企業担当者(総務・経営層)の皆様が抱きがちな疑問に答える形で、電気代上昇への対応策(補助金の活用や省エネ・再エネ対策、専門家への相談メリット等)についてQ&A形式でまとめました。北海道 電気値上げ 仕組みを正しく理解し、効果的な電気代削減策を講じる一助になれば幸いです。
基礎知識:託送料金値上げの仕組みを理解する
託送料金とは何か?
託送料金とは、電気を送電・配電するための送配電ネットワークの利用料金のことです。電力を小売供給する事業者(新電力や北海道電力などの小売電気事業者)は、一般送配電事業者(北海道電力ネットワーク株式会社)の送配電網を利用して電気を需要家へ届けますが、その際に発生する網利用料が託送料金です。託送料金は経済産業大臣の認可を受けて設定される規定料金であり、私たち需要家が支払う電気料金の中に託送料金相当分として組み込まれています。つまり、電気料金を構成する重要な要素の一つであり、インフラ維持や電力安定供給のための費用を支えるものです。
レベニューキャップ制度とは?
託送料金の算定には、近年導入されたレベニューキャップ制度が適用されています。この制度は、一般送配電事業者の必要な投資を確保しつつコスト効率化も促すことを目的とした新たな料金規制の枠組みです。具体的には、送配電事業者(北海道電力ネットワークなど)が策定する中長期の事業計画に基づいて、国(経済産業省)が当該期間における必要経費にもとづく収入上限(=託送料金収入の総枠)を認可します。
事業者はこの収入上限の範囲内で料金を設定・運営し、効率化の創意工夫を行いながら送配電事業を推進します。従来の「総括原価方式」と異なり、事業者の収入総額に上限が設けられる点が特徴で、需要動向や投資計画に応じて柔軟に収支バランスを取る仕組みとなっています。
託送料金はなぜ上がるのか?
今回、北海道電力ネットワークが託送料金値上げに踏み切る背景には、需要減少による収入不足と物価高騰等による費用増加があります。第1規制期間(2023~2027年度)の途中経過では、当初想定よりも電力需要が低迷し、特に単価の高い低圧(家庭用など)の需要減少によって託送料金収入が計画を下回る見通しです。一方で昨今の急激な物価上昇により、送配電設備の更新・維持や自然災害対応などにかかるコストは当初計画を大幅に上回ることが予想されています。
事業者側も経営全般にわたる効率化でコスト削減に努めていますが、それでも追いつかない収支悪化が生じており、このままでは計画していた設備投資や保全工事に支障をきたし電力の安定供給にも影響しかねない状況です。
そこで国の認可を得た上で、第1規制期間内の収入不足分を補填する形で託送料金を見直す決定がなされました。平たく言えば、「電力需要減で減収+コスト増」の穴を埋め、将来的な設備更新や災害対応・カーボンニュートラル投資を継続するためのやむを得ない値上げという位置づけです。
2025年10月からの託送料金値上げ幅
北海道電力ネットワークは2025年7月30日付で託送料金改定の届出を行い、2025年10月1日以降以下の新料金を適用する予定です。改定による電圧区分別の平均単価は次の通りで、低圧・高圧・特別高圧それぞれの1kWhあたり単価が5~6%前後引き上げられます(消費税抜きの単価):
- 低圧(主に家庭用・小規模事業向け):1kWhあたり10.23円(旧9.70円)へ +0.53円
- 高圧(中規模工場・ビルなど向け):1kWhあたり4.69円(旧4.42円)へ +0.27円
- 特別高圧(大工場・大口需要向け):1kWhあたり2.70円(旧2.57円)へ +0.13円
上記はいずれも平均モデル単価であり、契約メニューによって基本料金(kW契約料)部分など細かな改定幅は異なりますが、概ね低圧で0.5円/kWh、高圧で0.3円/kWh程度の単価アップとなります。全体として託送料金収入は約5~6%増加する想定で、北海道電力ネットワークの収入不足分(5か年累計259億円の見込み)を2025年度下期~2027年度にかけて補填する見込みです。
なお、この託送料金値上げが最終的に電気利用者の負担にどう影響するかについて、北海道電力の発表では家庭向けモデルで月額124円程度の値上げ(約1.2%の電気料金上昇)になると試算されています。
企業の場合は契約条件や使用量によって増加額は様々ですが、電力量料金部分が上記の通り上がるため、使用量に比例した負担増となります。例えば高圧契約で月10,000kWhを使用する事業所なら月約2,700円、月100,000kWh規模の工場なら月約27,000円の増加になる計算です。こうしたコスト増に対し、企業はどのような対策を講じ得るでしょうか。次項では、企業担当者が抱く疑問をQ&A形式で取り上げ、具体策を考えてみます。
FAQ:よくある質問とその回答
Q1: 託送料金の値上げで自社の電気代はどのくらい上がる?
A1: 自社の電気料金への影響は、契約区分(低圧・高圧・特別高圧)と使用電力量によって異なります。今回の改定では、電気1kWhあたり低圧で約0.53円、高圧で約0.27円、特別高圧で約0.13円の値上げとなります。したがって使用量が多いほど増加額も大きく、例えば月1万kWh使用する高圧契約の場合で月約2,700円の負担増、月10万kWhなら月約2.7万円の負担増となる計算です。電気使用量の把握と、値上げ幅(単価)の掛け算でだいたいの増加額を試算できますので、自社の直近の使用量を確認してみるとよいでしょう。なお、電気料金全体から見れば1%前後の増加に留まるケースが多いと想定されますが、今後の追加値上げリスクも踏まえ早めの対策検討がおすすめです。
Q2: 電気代削減のため、省エネ対策で効果があるのは?
A2: 最も基本的かつ効果的なのは、電力の使用量そのものを減らす省エネ対策です。使用量が減れば託送料金の支払いも減ります。具体的な施策としては、老朽化した設備を高効率なものに更新する、不要な照明や機器の電源管理を徹底する、空調設定や稼働時間を最適化する、といった取り組みが挙げられます。例えば古いボイラーを最新型高効率ボイラーに更新すればエネルギー消費が20%以上削減できる場合がありますし、照明をLED化したり高効率空調やエネルギー管理システム(EMS)を導入すれば10~30%以上の省エネ効果も期待できます。
そうした削減分がそのまま電気代削減につながります。また、契約電力(基本料金)の見直しも有効です。ピーク時の最大需要を抑制できれば基本料金部分の削減につながるため、製造設備の稼働を分散してピークをシフトさせるなど、負荷平準化の工夫も省エネ施策と併せて検討するとよいでしょう。
Q3: 再生可能エネルギーの導入は託送料金にどう影響する?
A3: 自社で太陽光発電などの再生可能エネルギー設備を導入し、自家消費することで、購入電力量(=託送料金がかかる電力量)を削減することができます。
例えば工場や倉庫の屋根に太陽光パネルを設置し発電した電力を社内消費すれば、その分だけ北海道電力ネットワークから受電する電力量が減り、託送料金の負担軽減につながります。再エネ導入には初期投資が必要ですが、国や自治体から導入補助金が用意されている場合もあり、賢く活用することで費用を抑えることが可能です。余剰電力が出る場合には売電による収入も得られますが、基本的に託送料金は電力系統を利用して送電する際に発生する料金のため、自家消費型であれば使った分だけ確実にコスト削減効果があります。再エネ設備の導入は電気代削減とカーボンニュートラルへの貢献という二重のメリットがありますので、補助金等を活用しつつ前向きに検討すると良いでしょう。
Q4: totokaに相談するメリットは?
A4: エネルギーコストの専門コンサルティング企業である株式会社totokaに相談することで、自社だけでは見落としがちな最新情報や最適策を得られるメリットがあります。totokaは北海道のエネルギーコスト最適化のプロフェッショナルとして、省エネ診断から補助金申請支援、最適な設備導入提案、導入後のフォローまで一貫してサポートしています。
豊富な知識と実績に基づき、各企業の状況に合わせた電気代削減ソリューションを提案してくれるため、託送料金値上げへの対策についても安心して相談できます。また、複雑な補助金申請手続きや効果の見えにくい省エネ施策の検討も専門家の視点で代行・支援してもらえるため、社内の負担を減らしつつ最大限のコスト削減効果を引き出すことが可能です。エネルギーのプロに伴走してもらうことで、単なる値上げ対処に留まらず、中長期的なエネルギー戦略の構築にもつながるでしょう。
まとめ・CTA
2025年10月からの北海道における託送料金値上げは、電気料金の仕組み上避けがたい措置とはいえ、企業経営にとって無視できないインパクトとなります。本記事で解説したように、託送料金値上げの背景には需要減少とコスト増という構造的な課題があり、その克服のためのレベニューキャップ制度の下での料金見直しでした。
値上げ幅は低圧で約0.53円/kWh、高圧で0.27円/kWhなど平均5~6%程度と一見小幅ですが、使用量次第では電気代全体を押し上げる要因となります。企業としては、電力使用量の削減(省エネ)や再生エネ活用による自給、自社に合った補助金の活用など、電気代削減に向けた多角的な対策を講じることが重要です。特に省エネ施策はコスト削減と温室効果ガス排出削減の両面でメリットがあり、中長期的な競争力強化にもつながります。
とはいえ、自社だけでエネルギーコスト削減策を計画・実行し、各種制度を活用するのは容易ではありません。そこで頼りになるのがエネルギーのプロフェッショナルです。エネルギーコスト削減でお悩みの際は、ぜひ株式会社totokaまでお気軽にご相談ください。北海道の企業向けに豊富な支援実績を持つtotokaが、貴社の状況に合わせた最適なソリューションと補助金活用の提案を通じて、持続可能な経営を力強くサポートしてくれます。電気料金高騰という課題に直面する今こそ、専門家の知見を取り入れながら賢く乗り切り、エネルギーコスト最適化と競争力向上を実現していきましょう。